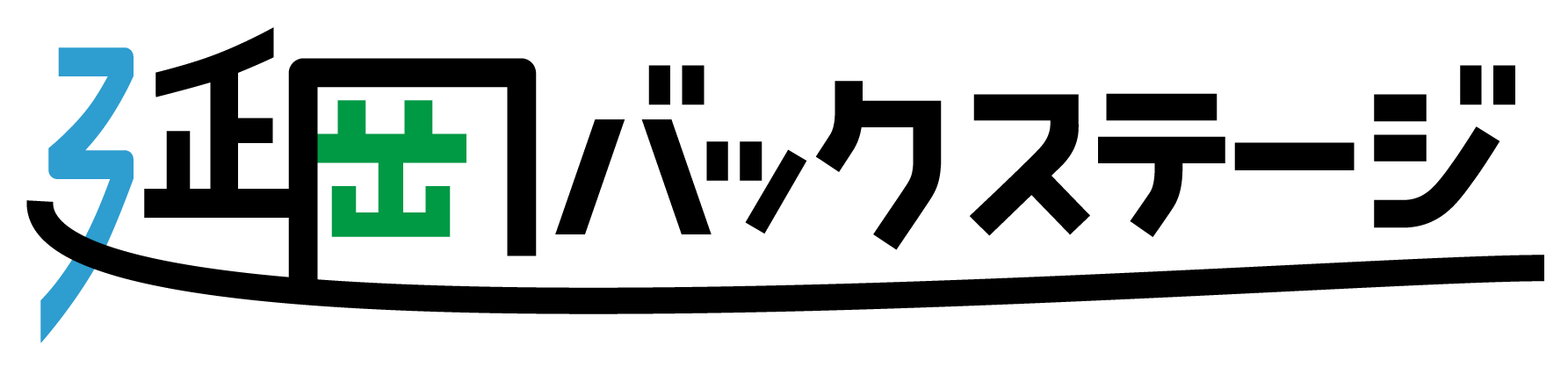一方で、観客が上演会場で劇場を訪れたかのような空気が味わえるように工夫し、作品の後半に視覚的な盛り上がりを持たせる計画も同時進行していく。
上演会場は、万博会場の東ゲートの入り口から程近いフェスティバル・ステーションと命名された屋内のイベントスペース。

常設ステージはあるもののショーなどを上演することを想定してはいないため、まずは劇場さながらのスペースへと様変わりさせていくために知恵を絞り出す必要があった。
こうしてステージの周囲に黒い布を張り巡らし、あたかも額縁の役割を果たすプロセニアムアーチがあるかのように仕立てるアイディアが考案される。
会場内を霧で包み照明の光線を浮かび上がらせる効果も持つスモークを通常よりも多く焚き、ステージと客席の一体感を神秘的に演出する手法もしかりだ。

舞台向けの特殊効果などの使用に万博サイドから厳しい規制を強いられる中で、フィナーレの視覚的な見せ場を設ける方法も協議を重ねながら検討されていく。
その一環として浮上したのは、ステージに立つ出演者の背後で巨大LEDスクリーンにCGを映し出し、臨場感を出すという案。
本番まで2週間を切っていたが、このフィナーレのCGを制作する人材を見つけなければならなかった。
こうして急遽プロジェクトに参加することになったのは、過去に延岡で手がけた6作品で映像デザインと制作を依頼してきた、宮崎マルチメディア専門学校の三橋幸四郎。
上演当日に不可欠なCGの微調整、そして映像投影の操作も彼が一手に引き受けてくれることとなった。

224名の出演者たちの年齢層と技術のレベルは幅広く、こうしたバトントワラーたちの個性も虹の色のように様々で、さらにはテーマ性が加味されているのがショー最大の売りとなる。
そこで必要不可欠となったのは、この類のライブエンターテインメント作品では珍しい台本の作成。
ステージングの流れや動き、使用曲での照明のイメージなどといった詳細が記され、日を重ねるごとに加筆されていった。
同作品には2024年の世界大会のメダリストとなる関西のバトントワラー4名がゲストとして出演するが、彼らが虹の精霊の役割も果たす運びとなったのは、ショーが仕上げの段階に入ってからのこと。

ショーの冒頭では降り頻る雨の音を背景に、青山弥生によるナレーションが客席に響き渡る。
雨 それは空から舞い落ちる 水のしずく
大地を潤し 草花を芽吹かせる 天からの恵み
時には脅威にもなり すべてを洗い流す
雨上がりの空 七色の光が降りそそぐ
未来へと向かう旅の架け橋
それこそが天空を彩る奇跡 虹
すると、ナビゲーターとなる高見亜梨彩が虹をイメージした傘をさして登場、そこから一本のバトンを取り出すのをきっかけとして20分のパフォーマンスが始まる。
バラエティに富んだバトントワーリングのパフォーマンスが、虹にまつわる様々な楽曲を使って披露された後にフィナーレが近づくと、出演者全員が順番に次々と登場、スモークが注入された無数のシャボン玉が宙を舞う。シャボン玉がはじけると、そこからはスモークが放出され幻想的な空間が客席を包み込む。




次に出演者たちの頭上に“逆さ虹”を具現化した大道具が飛翔しながらかかり、その背景で三橋幸四郎がデザインしたCGによる色とりどりの虹色の粒子がステージの床から天井に向かって勢いよく登っていく。
出演者の各々が思い描く、虹の彼方に向けた未来への願いが示唆される瞬間だ。
カーテンコールの終了後は、ショーに携わった出演者やスタッフ全員の名前が映画作品のようにエンドロールでスクリーンに映し出される。
プロデューサーたちを驚かせたのは、このエンドロールが終わるまで観客たちが客席から立とうとしなかったこと。
公演は3回にわたって行われたが、追加席を用意したにも拘わらず、出演者の家族や友人でさえ観ることができない盛況ぶりは想定外だった。

昨今はスポーツ競技界における閉鎖的な側面が指摘されることが多い。
バトントワーリングにおいても例外ではなく、マイナス面に目を向けた報道が行われることもあるのが現状だ。
競い合うという概念を撤廃、スポーツがライブエンターテインメントと融合し、相互関係を保たせるのは高いハードルとなる。
そんな中、224名の出演者が情熱を傾けた『EXPO 2025 バトントワーリング・フェスタ』は、競技という世界を超えるバトンの新たな可能性を次世代へと託す試みとなった。